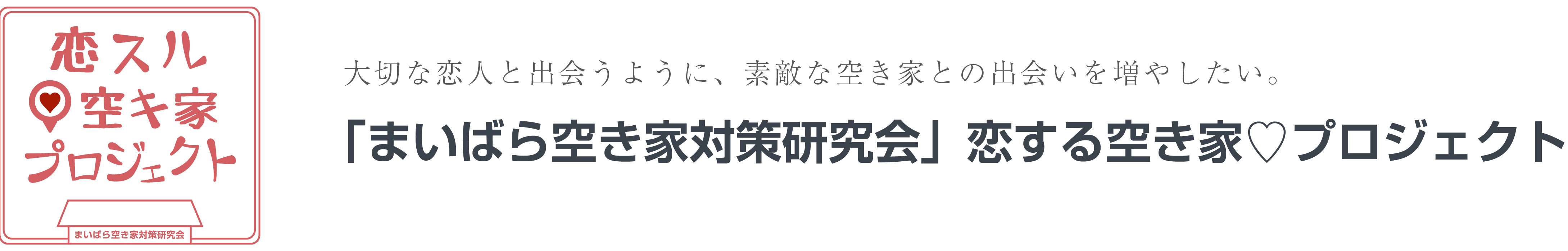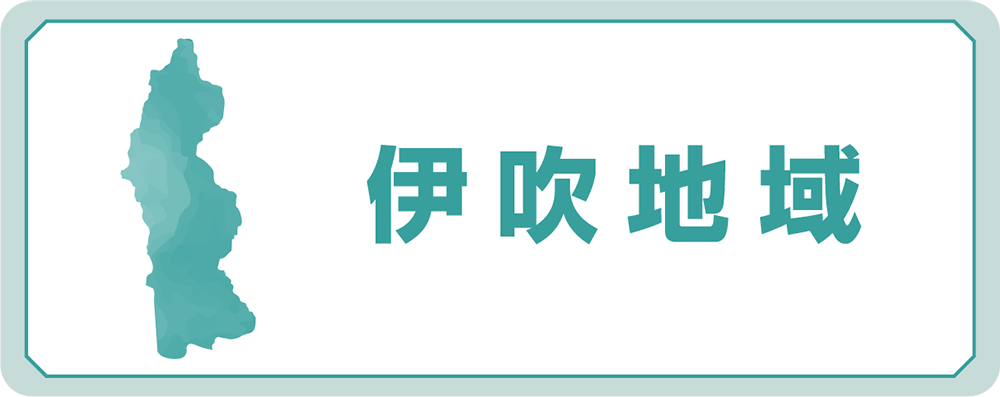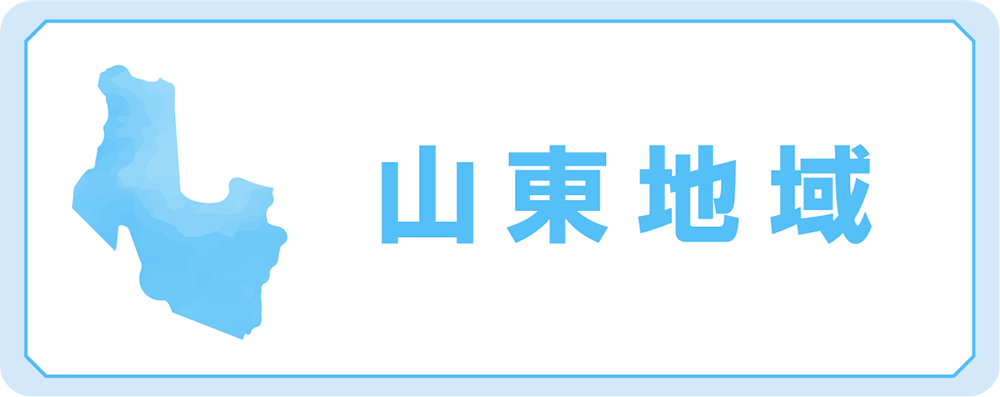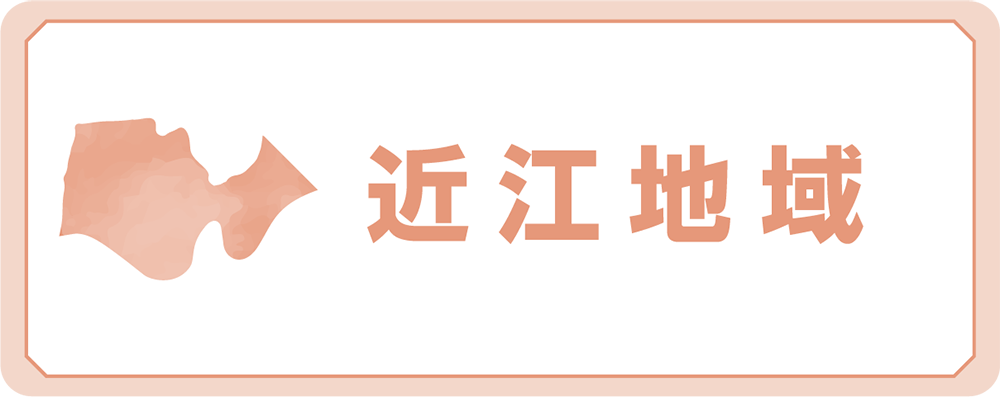湖北地方の冬のおやつ「かき餅」づくりを教わりました

こんにちは!みらいつくり隊 あさいです。
寒い時期になると、保存食づくりが盛んになります。
先日、地元の方のお宅にお邪魔して
「かき餅」づくりを教えてもらいました!
かき餅とは?
かき餅とは、薄く切って乾燥させた餅のこと。
神が宿るとされる鏡餅を親族で分ける際に、
刃物で切るのではなく手や槌で割ったり、
小さく欠いた利したことが欠餅⇒かき餅となったことが由来なんだそうです。

見た目はこんな感じ!
油で揚げたり、やいたりして食べます。
寒い時期に仕込むので、
冬になると各家庭で見られる光景なんだとか。
湖北の冬のおやつとして有名です!!
わたしも引っ越し当初、道の駅で買ったことがありました。
地元の方に教えてもらえるなんてわくわく!
①もち米を蒸す
滋賀のもち米で有名な品種「滋賀羽二重」。
道の駅やスーパーに並んでいます。
羽二重餅、って、福井でしか聞いたことなかった!
もち米の名前だったんですね。
蒸し器(もしくは餅つき機についた蒸し機能)で、もち米を蒸していきます。

蒸したて!もうおいしそう…。
餅つき機へ移動。
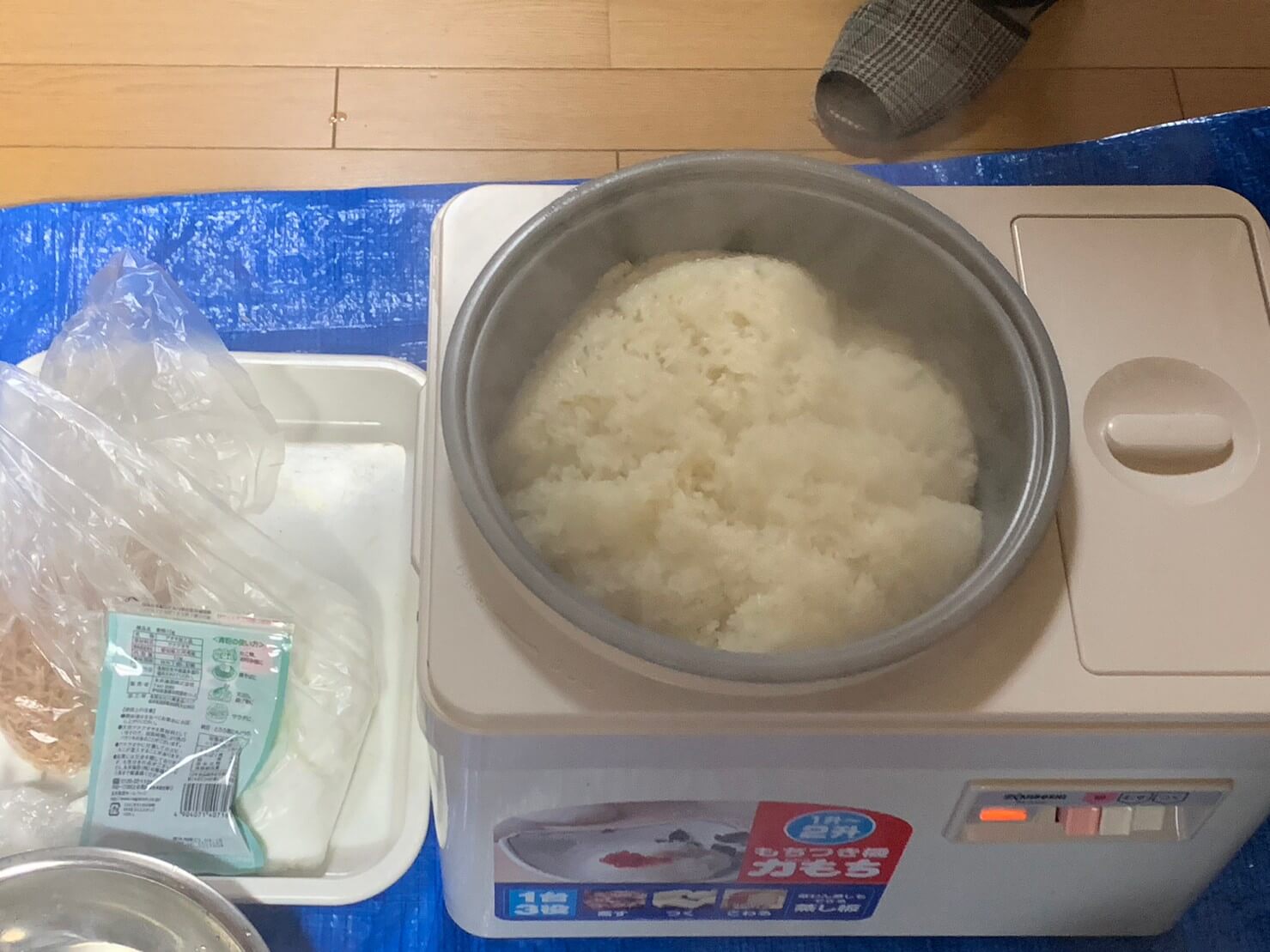
炊き立てご飯の、いいにおい!
※湯気で曇ってます。
②餅をつく
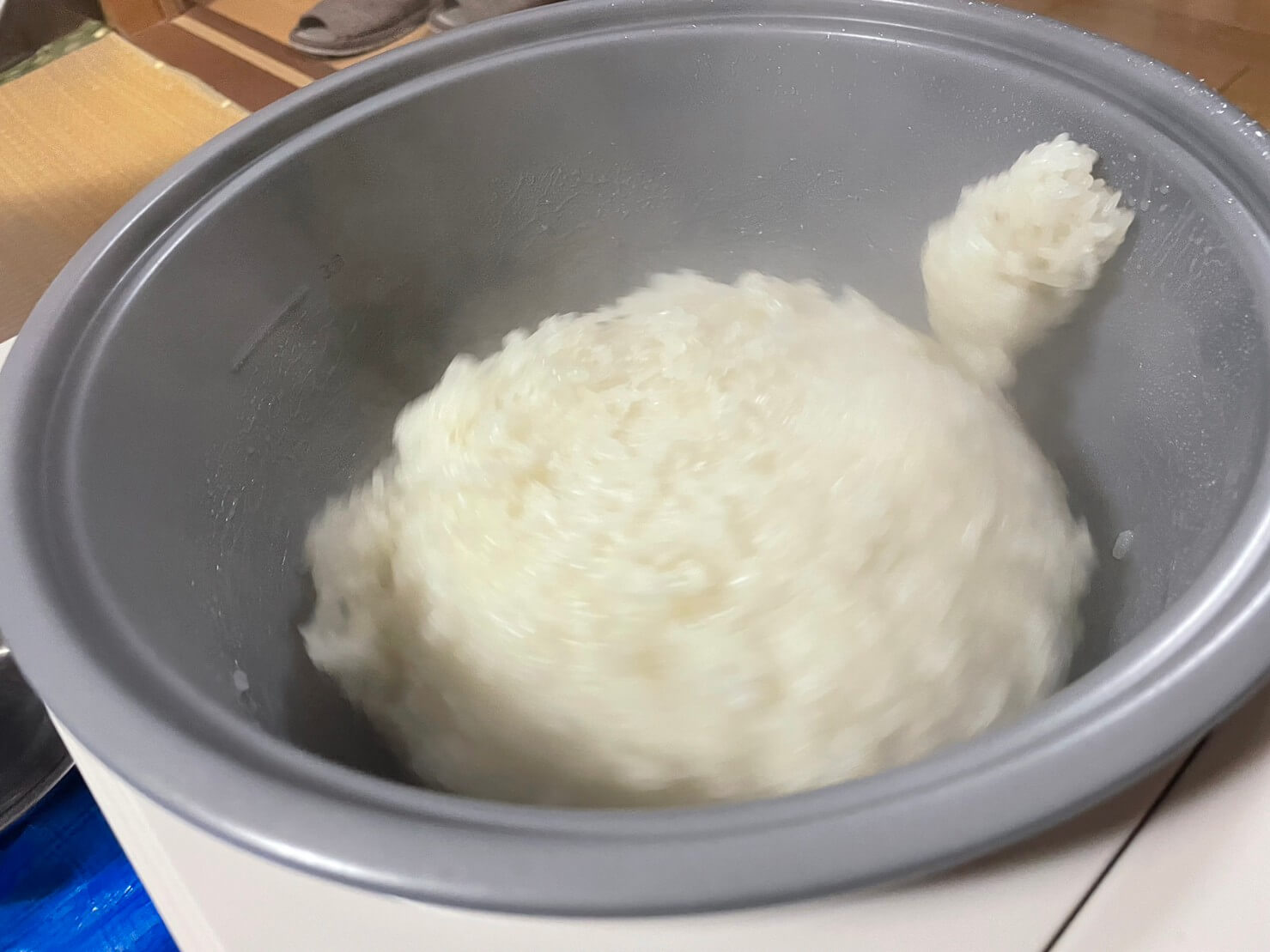
餅つき機に入れて、高速回転。
どんどんおもちになっていきます。
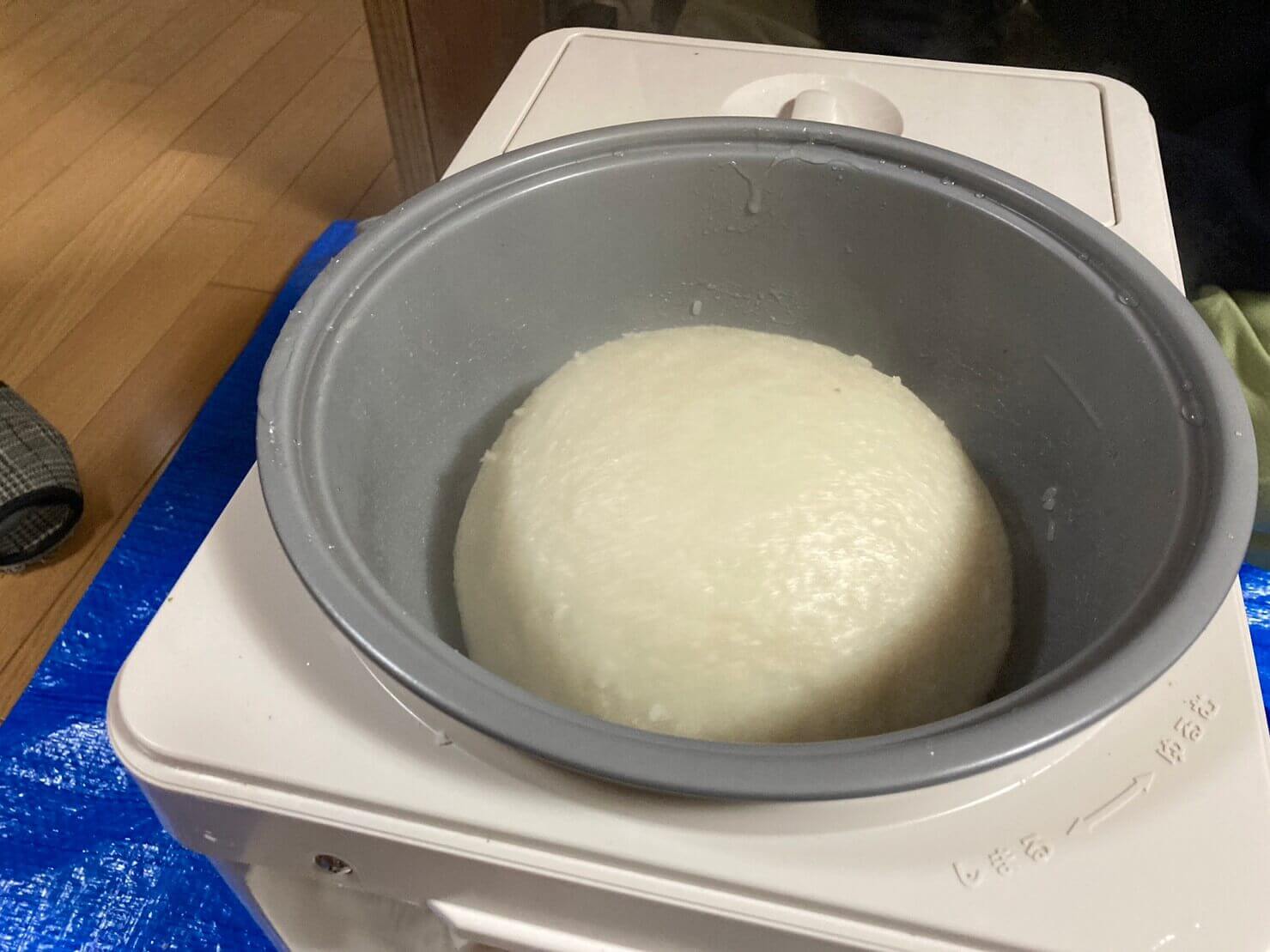
このなめらかさ。か、かわいい…癒し…
どんどんもち米が餅に変化する様子は面白く、一日中見てられそうな感じでした。笑

塩・砂糖。
けっこうな砂糖の量です。味付きのおもちになります。

ベーキングパウダーも入れます。昔は山芋や里芋で作っていたとか!
滑りが悪くならないように、水気を足しながら回し続けます。
餅つきの時の「手水」のような役割。
③味を投入
かき餅は、カラフルでいろんな味付けが楽しめます。
今回は、「エビ×青のり」と「昆布」。

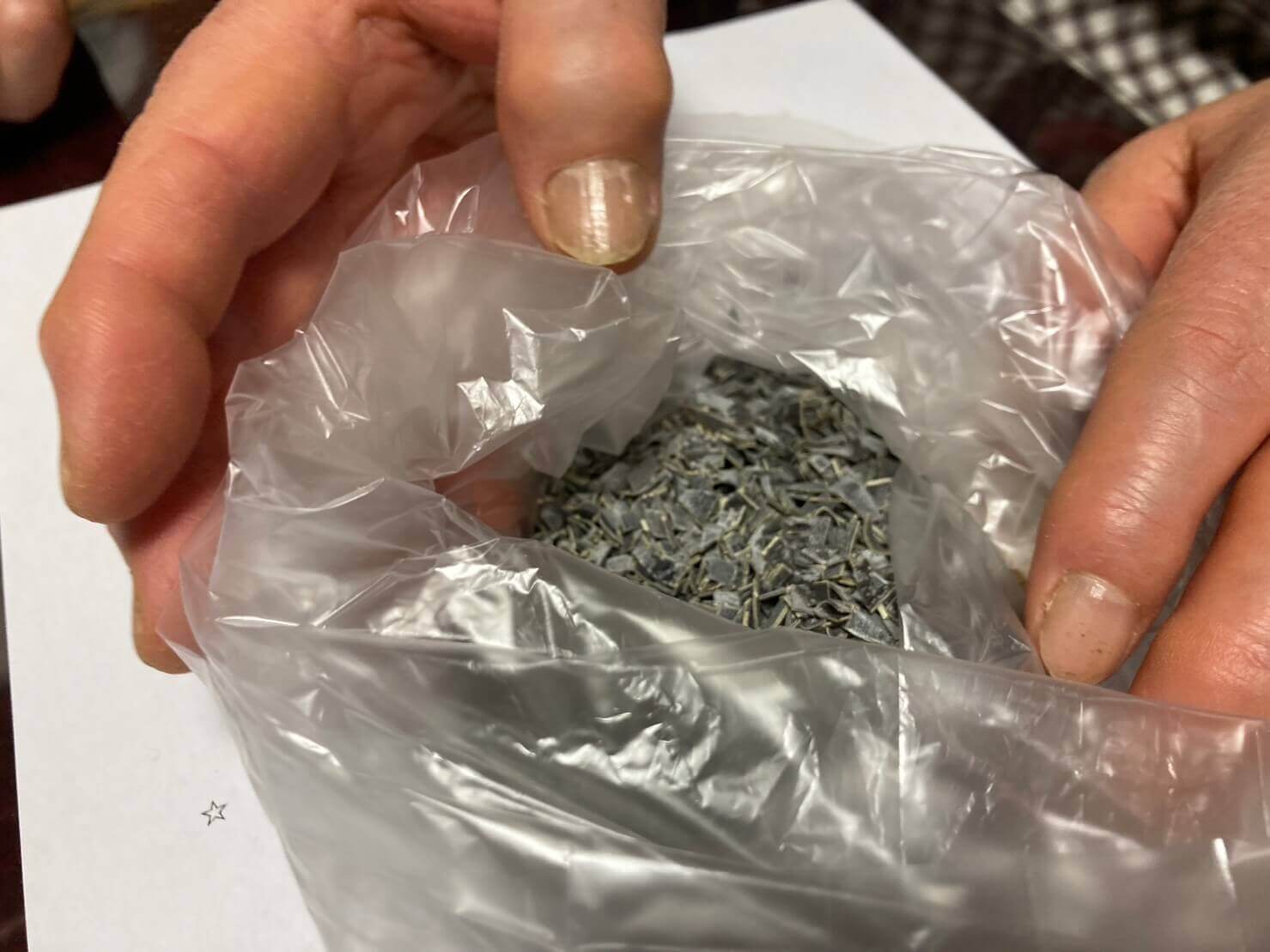
他にも、落花生・大豆・山椒・梅・カレー・柚子・チョコレート・生姜・ヨモギ・チーズ等…
アレンジは無限大!
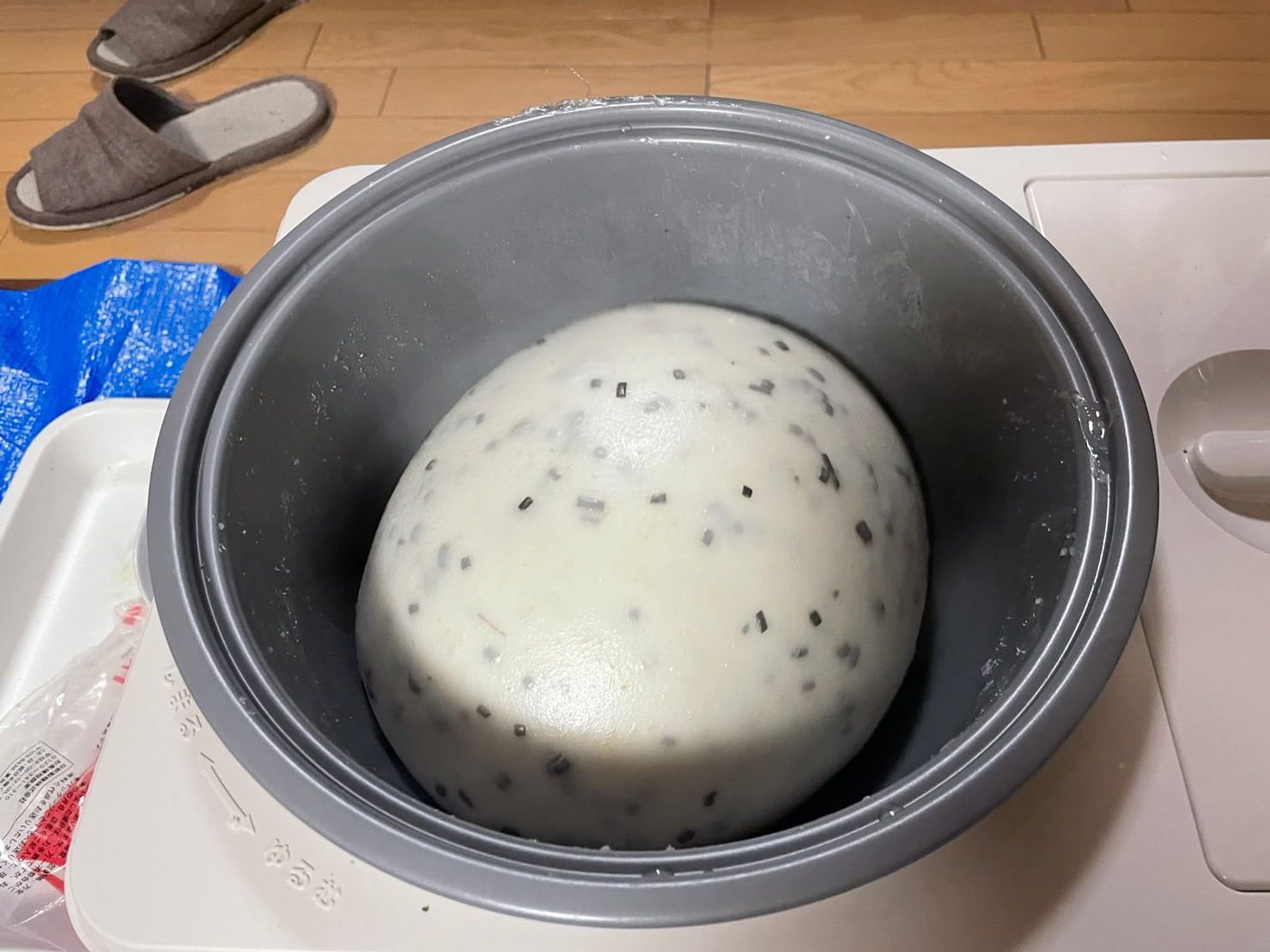
昆布サッカーボールみたい~
④箱に詰める
かき餅の四角い形は、ここで登場する木の箱に詰めて固まらせることで作ります。
この箱、ぴったりになるように研究を重ねて作った手作りなんだとか!
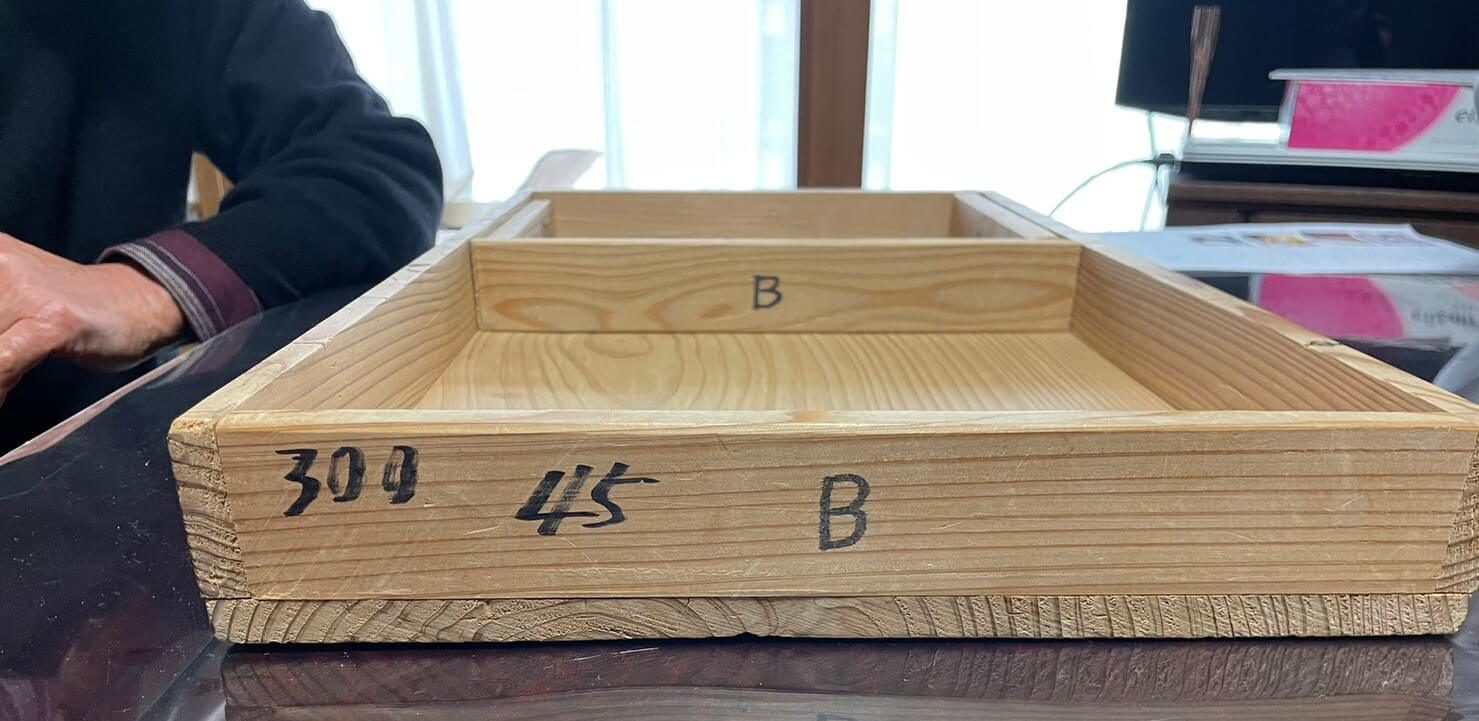
まだ温かく、柔らかい餅を詰めていきます。
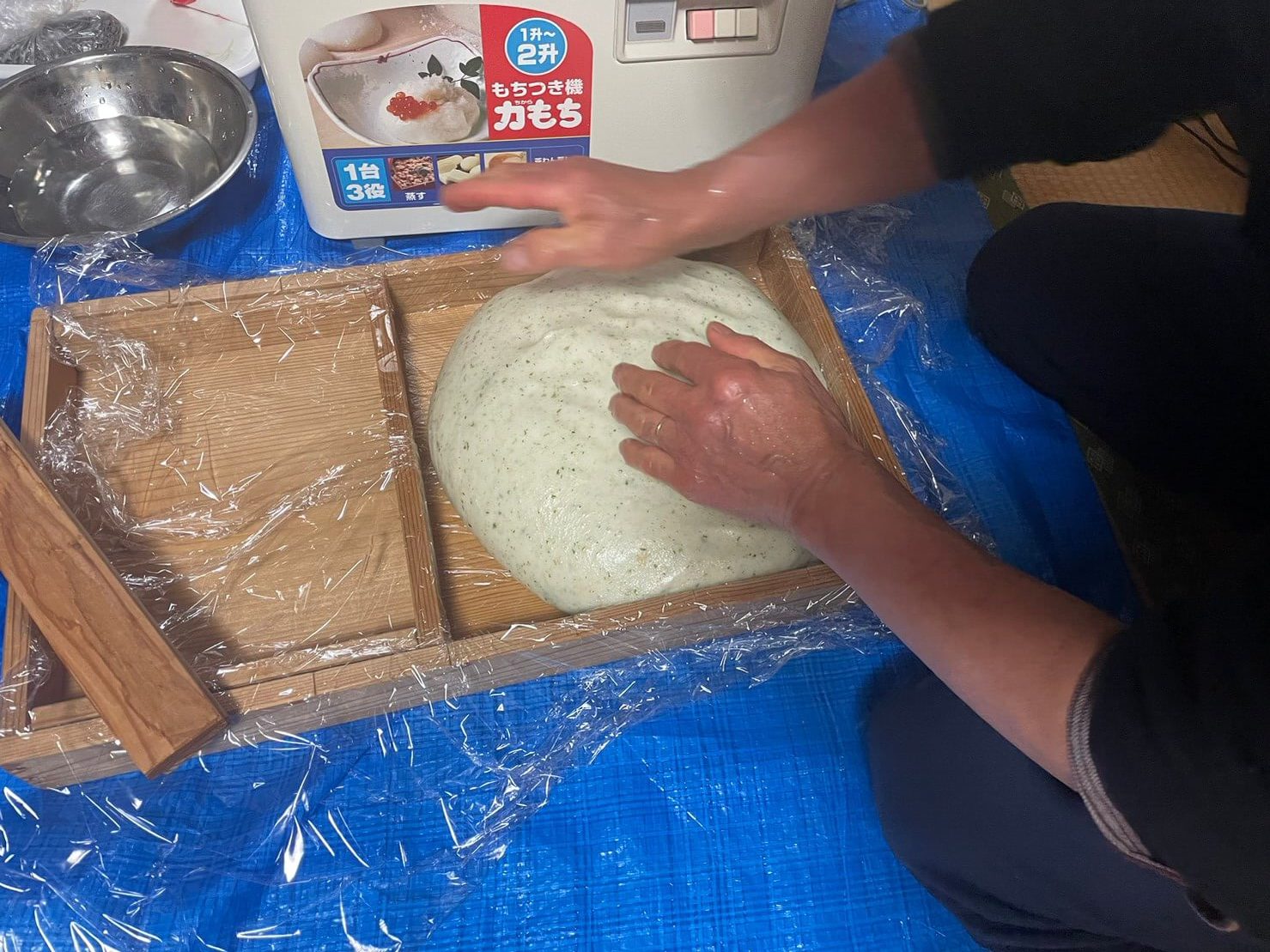
角まで押し込むことがきれいな形をつくるポイント。
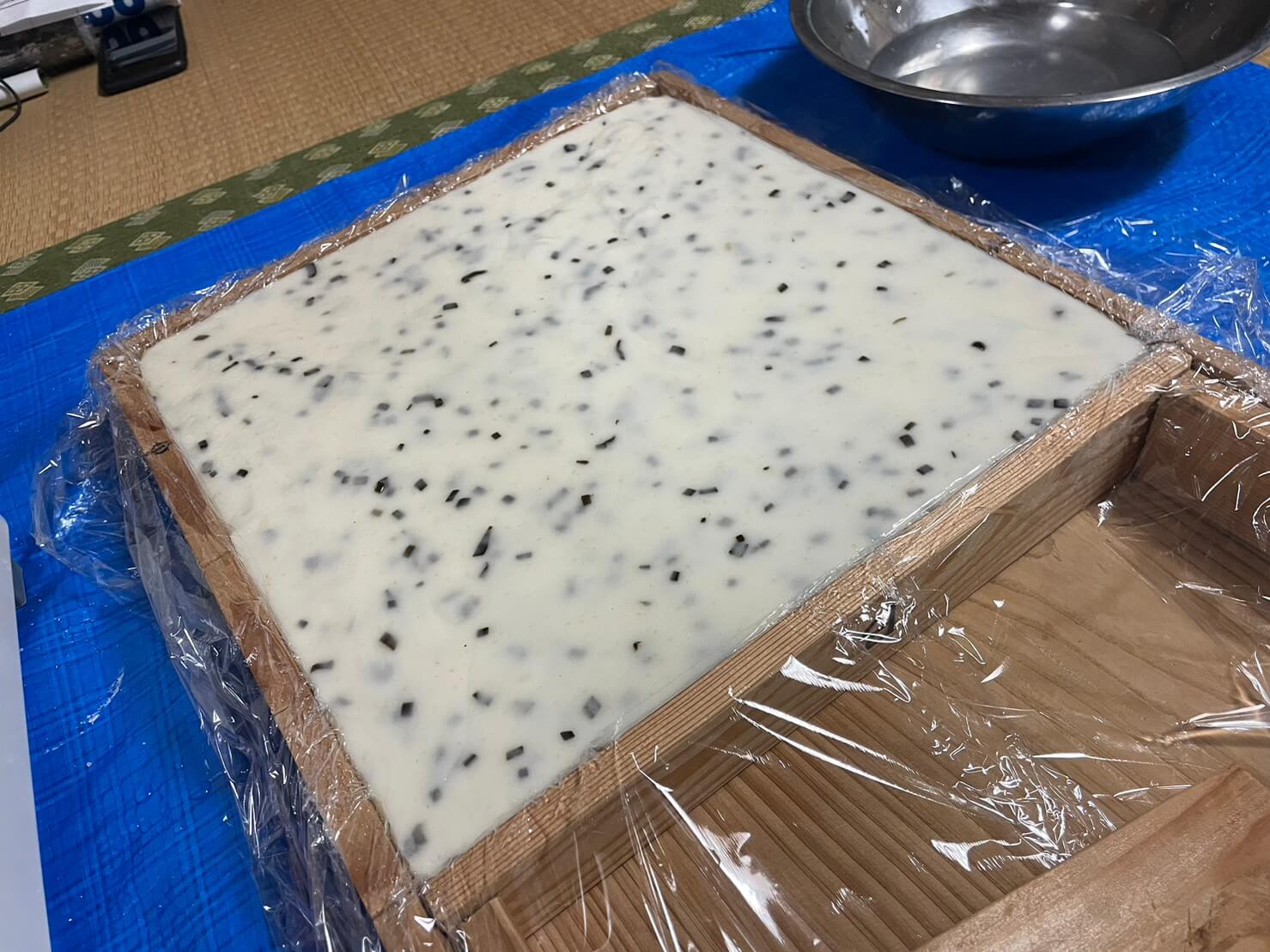
ここまでできたら、縁側等、直射日光の当たらない場所で乾かします!
⑤切る
乾かすのには日数が必要なので、
今回は既に乾かしてあるかき餅で、もち切り機の体験もさせていただきました。
こんな大きな刃で!薄く切っていきます。すんごい気持ち良い切れ味。

⑥干す
切った餅は、棚に並べるか、
こんな感じで紐で編んで吊るします!(本来はもち藁)
乾くにつれてだんだんと縮んでくるのを家でも楽しんでいます♩

はしっこ
切って余った端っこは、細かく切り分けてあられに。
小さくて食べやすいし、コロコロかわいい!

⑦食べ方
食べるときは、
レンジで。トースターで。
油で揚げて。いろんな調理方法があります。
昔は火鉢の上で焼いていたと言います。
調理方法によって食感や味も変わるので、楽しいし飽きません!
田舎のごちそう
この日は、かき餅だけでなく
地元の郷土料理もいっぱいごちそうになりました!
田舎のごちそう…
特に私は、初めて食べた「鮒味噌」の美味しさにはまりました。。。
ご飯がすすむ。みんな、おかわりしてました。笑

手作りのこんにゃく。いろんな味の味噌。漬物。鮎。山菜…

畑で育てた大根の入った、おでん。
幸せな時間でした…
わたしも、つくれるようになりたい!!!
今年は、野菜も育ててみたいし、
こんな手仕事ができるようになっていきたいって思いました。
郷土料理や田舎の食文化・・・魅力的です。
また、田舎の知恵や味を教えてもらおうと思います!